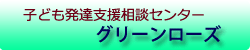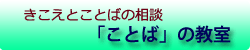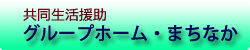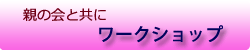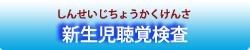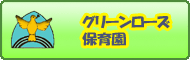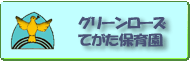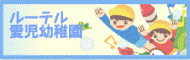Category Archives: 理事長ブログ
支援とは何か
長くグリーンローズホームページのブログに手をつけないできました。もし読まれてこられた方がおりましたら、深くお詫び申し上げます。令和4年1月以降、全く手を入れないまま過ごしてきました。しかし、その間にもたくさんの出来事があり、書きたいこともいっぱいありました。しかし、なぜ手をつけられなかったのかは、令和4年が社会福祉法人グリーンローズ創立50周年ということもあり、そのためなかなか手をつけられなかったことが挙げられますが、自己弁護のようにも思われますが、この間の状況を少しだけ振り返ってみたいと思います。
平成18年頃から、社会福祉事業制度の大きな変換期を迎えました。その大きな揺籃を経て、平成25年頃におおよその姿が固まりつつありました。しかし、それが令和にまたがって社会福祉事業の更なる揺籃を生み出したと言っていいのではないでしょうか。「障害」のある人々の生活、支援を必要とする子どもたちへの制度の整備は必須だったと思われますが、新しいものを作っていく産みの苦しみは今も続いているように思えてなりません。
私達社会福祉法人グリーンローズは、創設者片桐格先生の理念のもとに作られ、運営されてきましたが、基本的な考えは変わっていないと思います。それは「共に生きる」という一言に尽きると考えています。この世界に生まれ、たとえば「障害」があっても無くても「共に生きる」、子どもたちにおいても発達や身体に支援を必要とする子どもも、そうでない子どもも「共に生きる」これが求める世界、今も変わっていないと確信しています。
社会福祉法人グリーンローズ支援部は、様々な家族、特に支援を必要とする子どもたちを持った家族とその子どもたちを支援してきたと思っています。ところで、私たちは何を支援してきたのでしょうか。私たちは長い時間をかけて、子どもたちの成長・発達がよりすみやかにいくように、多くの実践や技術などを学び手に入れてきたことは確かです。子どもたちの成長・発達についての研究などについても学んできました。保育の技術、また学校との連携、言語へのかかわり(言語聴覚士)、運動への関わり(理学療法士・作業療法士)、心理的なものへの関わり(心理療法士)等々。それでも、私たちは子どもの何を支援しているのだろうかという疑問は次々に浮かんできます。
私はひとつの提案をしたいと思います。それはごくあたりまえのことで提案などというとおこがましい感じになってしまいます。でも、あえて私は次のように言いたいのです。「子どもと出会えておりますか?」と。これは、私たち支援をする立場の人間だけではなく、すべての子どもと関わる人々に問いたいのです。私たちは子どもたちが多くの人と出会うための支援をしているのではないか、と思うからです。そして元気に生きていけるように支援する、それは様々な人と出会うことが何よりのことだと思うからです。
お母さんの手の中でこちらを見ている子どもたち、お父さんに手を引かれてこちらを見ている子どもたち、その目の中にどんなものが見え、どんなことを考えているか、想像するだけでワクワクしませんか。もちろん人がなかなか入りにくい子どもたちも、特定のものに惹かれる眼差しもあるかもしれません。でも、ここに会いたい人がいますよ、と時間をかけて「出会う」こと、目が向かうことなどが基本的な支援と私は考えています。
新しい制度が、こうしたことをしっかりと包摂した制度であることを強く願っています。
次回は、できるだけ早く片桐格先生に出会い、そこに惹きつけられ、子どもたちに惹きつけられ、今日まで過ごしてきてしまった自分について思いを巡らしたいと考えています。
合理的配慮 令和4年1月15日(土)ワークショップに思う
グリーンローズワークショップは、インクルーシヴのための学習や啓発のために企画され、長く行ってきました。
地方の小都市、この秋田で昭和54年(1979年)「養護学校義務化」以降、数は少なかったのですが、支援を必要とする子どもの中で、毎年地域の学校に入りたいという子どもとその家族がおりました。その旨を教育委員会に伝えてもほとんど見向きもされなかったのです。そのため、小さな会(その中には親の会、市会議員などが含まれていました。)を作り、毎年のように交渉を行いました。しかし、全て教育委員会の意向を呑まなければなりませんでした。昭和60年(1985年)に同様の事態が、ある兄妹に起こりました。先天性筋ジストロフィーという「障害」をもつ兄妹でした。この時この活動に同調してくれたある新聞記者が紹介してくれたのが、弁護士大谷恭子先生でした。日本で最も早く就学の問題を取り上げ、地域の学校へ!をスローガンにし、日本各地でのこうした活動に弁護士の立場から積極的に取り組まれた方だったのです。
私(後藤)は全国の活動を熟知していたわけではなかったのですが、日本の各地で、そのような動きがあることは知っていました。しかし、その中心にいた大谷恭子弁護士がこの秋田の問題に関わってくれるということを聞き、大きな励ましと力を得たように思ったものでした。家族の粘り強い活動は、1年半の運動の後、兄妹は地域の通常学級に入ることができ、6年生まで過ごすことができました。
私たちグリーンローズは、法人ができた時から「来るもの拒まず」という創業者片桐格先生の想いを実現したいと思いながら活動してきたつもりです。ある時は「統合保育・統合教育」、ある時は「メインストリーミング」など、言葉は変わりましたが、まさしくインクルーシブ(排除しない)を目指してきたと言って過言ではありません。そうした想いがワークショップとして、自分たちも地域の人も共に学び、共に啓発していこうという試みでした。
大谷恭子先生には、これまで2回ほどワークショップに来ていただいておりました。今、私も現場を辞そうとする時にもういちど大谷恭子先生のお話を聞きたい、皆に聞かせたいと考えて、今回のワークショップになったのです。
話題は、現在抱えている就学問題の裁判、「権利条約」批准後の「合理的配慮」についてどのように考えればいいのか、という現実と理念との架け橋を細かく解説していただきました。
大谷先生は、「障害のある人の権利に関する条約(川島聡・長瀬修訳 仮訳)「障害者の権利に関する条約(政府訳)」に出てくる「合理的配慮」とは何か。どのような意味があるのか。そして権利条約の根幹となる「合理的配慮」とは、とその内容を会場の皆の意見を取り入れながらの講演となりました。権利条約の理念がどのように現実の社会で実現されていくのか、このことが大きな課題です。現に抱えている裁判があったのに(学校に入れない、入れてくれない)、裁判の結果を待てないと、保護者は入れてくれる学校に探し、転校したところ、まことにうまくいっているケースを紹介し、いったいこれは何なんだ?というお話でした。子どもの住んでいる場所の学校により受け入れが違うこと、子どもたちの権利は、この日本という社会においてどうなっているのか?大いに考えさせられたワークショップだったと思います。
およそ秋田の先天性筋ジストロフィーの兄妹の闘いに大谷先生が駆けつけてくれた時から、35年もの月日が経ちました。それにもかかわらず、日本の教育のインクルーシヴは分離を制度化・整備化し、分離の現状を固定化しています。少なくともインクルーシヴの未来への道筋を明らかにし、そのための教育制度の改革を目指すべきなのではないでしょうか。
長い時間が過ぎました
長い時間が過ぎたように思います。またそれはあっという間のようでもあります。私は、来年の10月をむかえると、この職場に入り50年の時を迎えます。来年50年を迎える前に、現場は辞させてもらおうと思っておりますが、最近、自分のこれまでの仕事を考える時がよくあります。自分の生い立ちと重ね合わせて考えてしまいます。この機会に少し自分の生い立ちと両親について書いてみたいと思います。
母について
私の生まれた村は、秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字滝ノ沢下村というところです。母は戦争から帰った父と結婚し、私を産みました。母は、戦争前から東京に看護師の勉強に出かけ、戦争が激しくなる前に看護婦(師)・保健婦(師)・助産婦(師)資格を取り、帰郷し、主に助産婦(村では産婆と言っておりましたが)をしておりました。母は貰われっ子で、子どものいなかった義理の祖父母(私からみて)に、ずいぶん可愛がられたと聞いています。しかし、母がある時その義父に「医者になりたい。」と告げたところ「女が医者などになるものでない。」と拒絶され、看護師だったらということで、看護師の道を選んだと言っていたのを覚えています。明治25年生まれの祖父、圧倒的な東北の山村の生まれで、三反農業の祖父に、当時の通念的考えの変更を求めても無理だったのではと思っています。それでも医学に関わる仕事を求めた母は、尊敬に値すると思っていました。母は、東京のいまも吉祥寺駅前に残っている水口医院で見習い看護婦から始め、千葉で試験を受け合格したとのことです。
村にはおおよそ集落群の中心(肴沢地区)に一つだけの診療所がありましたが、車もない時代、救急の患者さんの家族はよく家に駆け込んできました。診療所の医師とは連絡を取り合っていたのだと思いますが、現代から見ると不正医療行為だったのはないかなどと思ってしまいます。それでもうちに駆け込んでくるということは頼りにされていたのではと思っています。お産などがあったときは、ほとんど徒歩で向かうため、3日ほど帰らないことはザラでした。祖母が元気なうちは特に問題がなかったのですが、私が小学1年生の時に脳溢血となり、一度はほとんど回復したのですが、2度、3度と繰り返し次第に症状も重くなって行きました。そうなると、お産の手伝いに出かけた母のいない家は何ともご飯のおいしくない献立に参った記憶があります。
母は私の進路に対して医療への道のことなど一度も話したことがありません。私の能力がわかっていたのかもしれません。ただ私は母の仕事を間近で見ながら、こうした仕事は決してやりたくないと思っていたことは確かでした。そういう意味では、漫然と子ども時代を送ったと言えると思います。「医師」という方々への母の尊敬の念は終生変わりありませんでした。
母は文学も好きで、自分の好きな作家や、詩人のことをよく私に話して聞かせてくれました。与謝野晶子の「君死にたもうことなかれ」、石川啄木、中原中也の「汚れっちまった悲しみに」など読んで聞かせてくれました。それらは私の手には負えなかったのですが、話し相手のいない対象として私が選ばれたのではと思っています。そのおかげかどうか分かりません、若き頃、中原中也などはよく読みました。母の一番好きな短歌は石川啄木の「函館の青柳町こそかなしけれ 友の恋歌 矢ぐるまの花」は今でも諳んじることができるほどです。その後母は、地方の小都市の総合病院に勤めていましたが、私の順調でない人生を心配しながら52才で亡くなりました。肺化膿症という病気でした。自分を育ててくれ、既に亡くなっていた義父の元に行く、という日記を残しておりました。
父について
父は、同じ村の私が入った小学校の教師でした。「ゴリラ」というあだ名がついていたのは、学校に入ってから知りました。後に私のあだ名は「ゴリラのこっこ(子ども)」になりました。私は父が同じ学校にいるのが嫌で嫌でたまりませんでした。そうした中、小学3年生の終了とともに他の学校に赴任して行きました。その後の父の変わりようには子ども心に驚いたものです。村の小学校にいた時は、結構遊び人で、パチンコをしたり、家具を作ったり、当時珍しかった自転車を買ったりと、好きなことを勝手気ままにやっていた印象だったのですが、学校が変わった(西成瀬小学校=共通語教育)ら、人も変わったように、夏休み・冬休み全くないほど学校にのめり込んでいったのです。しかし、西成瀬小学校に39歳の時、教頭で赴任したのですが、結局退職まで、万年教頭で終わりました。これは学歴もなかったことや、西成瀬小学校の教育が、文部省が推薦しない教科書を使ったりしたことも理由だったのではなかったかと思っています。私はそれこそ勲章でしょう、と言ったこともあります。私の進路に指図らしきことを言ったことは一度もありません。秋田大学に入る時、私は少し駄々をこねたのですが「教師だっていいじゃないか。」と言ったのが唯一の言葉でした。私が大学で大学を相手の運動に参加していたときに、父が大学に呼び出されたこともありました。他にも呼び出された父親がいましたが、ほとんどが拒否したようでしたが、私は組織と関わりなかったので、父に任せたままにしました。父は深く考えることもなく、呼び出されたために、大学にやってきただけと思います。様々なことを言われたとのことですが、「息子には息子の考えがあると思う。」と答えたとのことです。私はその後、大学に行かなくなり、学生たちの大きな運動の後、あちこちで働くようになりました。そんな中、沖縄行きの話が出ました。母が入院していた病院の屋上で、「あまり父さんに心配かけるなよ」と言われ、それが母との最後のやりとりになりました。結局沖縄には行かず、母が亡くなった次の年、現在の職場に拾われたのです。
父は教職退職後、保育所の園長になり、保育所協議会で頑張ったようです。保育は、私が勤めた職場とは大いに関係が深く、その後よく話ができました。父は自分の持っている能力、絵画、書道、ガリきりなど、またタイプを購入し必死に園通信などを打っていたのを覚えています。結構楽しかったようです。最後には、勤めた小学校教員時代にガリきりの学校通信を出したものをまとめ、「野の学校の記録」として出版しました。父は「これをまとめたら自分は死ぬんではないか。」と言っていたその言葉の通り、出版後、間もなく腹部大動脈瘤破裂で亡くなりました。83歳でした。
こうした自分の来歴を考えながら、自分の仕事をみてみると、両親の仕事であった医療や教育という世界を無意識のうちに感じてきたのかもしれません。私を拾ってくれた片桐格先生は、私にアメリカで見てきた医療と教育(保育)の連携を熱心に語ってくれました。片桐格先生は、その話をする時には遠くを見るような眼差しでした。その時からは、いつの間にか50年という歳月が過ぎようとしています。医療と保育、医療と発達支援、医療と教育、それらの統合・連携という、まさしくそうした時代が日本においても身近になったのです。
最近、無性に祖父(兵吉)祖母(トミノ)、そして父(岩雄)母(キサ)に会いたいと思うようになりました。叶わぬ夢であることは知っているのですが。 2021年11月29日
山登り(雄長子内岳470m)
私が山について心惹かれたのは、1977年(昭和52年)東京の早稲田にありました国立聴力言語障害センター附属聴能言語専門職員養成所で研修を受けていた時のことです。夏に同期で私より4歳下の和田さんという方に山に誘われました。全員5人で、南アルプス鳳凰三山に向かい、左側に日本で二番目に高い北岳を見ながら登ったのです。本当に山に魅せられました。
この時、私は新宿で電車を待つ間、和田さんが借りてきてくれた登山靴をうっかり置き忘れてしまいました。深夜、甲府の町中で登山用具屋さんを探し、代わりの登山靴を買い求めたりしました。大事な登山靴を無くしてしまい、和田さんにも大きく迷惑をかけてしまいました。この場を借りて深く謝ります。申し訳ありませんでした。
そんな中でも、山は素晴らしく、私を惹きつけてくれました。秋田に帰ってから、自閉症親の会の主催で、温泉登山旅行を何年もお手伝いさせてもらいました。また、オリブ園のわんぱく運動教室で、年1回の太平山登山を25年間も続けました。秋田の山の会「ルートファイブ」(太平山登山ルートが5つあることからつけた名称)の石井初男さんのお力添えがあったことが大きかったです。石井さんは残念ながら亡くなってしまいました。
私も後期高齢者の仲間入りしてしまい、体力のこともあり、秋田周辺の低山の散策を時々しております。ワンちゃんと二人でゆっくりとした登山で、大とら組(中学校以上放課後等デイサービスインクル)の登山の下見も兼ねて楽しんでいます。
今秋は少し遠いのですが、湯沢市皆瀬の「長いスプーン」(社会福祉法人)にお邪魔する時、途中向かって右側に素敵な山があり、ネットで見ると地元のマッターホルンと呼ばれているようです(笑)。そのためいつか登りたいと、二度程出かけました。しかし、登山口を見つけ切れず(国土地理院の地図では)撤退してきました。その後、後期高齢者直前の9月19日にネットで探した登山口を見つけ、登ることができました。以下、PDFでご覧ください。