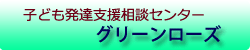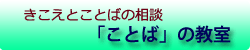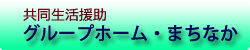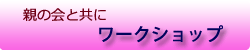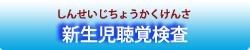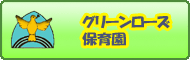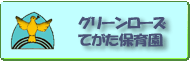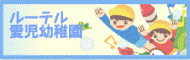「明るいの反対なーんだ?」
最近、「コロナ時代のパンセ」辺見庸 を読んだ。時代を捉えて厳しい言葉の一つ一つが、突き刺さるような文章に心打たれるのは、かつても今も同じである。むしろ激しさを増したと言えるのではないだろうか。コロナ禍の世界がどのような方向に向かうのか、そうした危惧について、自分の立っている場所を振り返させる力がある。コロナ禍の始まりの時点での文章で、おおよそ首相交代時点での出版となっている。もう少し先までの文章をぜひ、と私は強く願っている。
彼が、介護老人保健施設に通い始めて1ヶ月のことが書かれている(2019年)。そこでのトレーニングについてである。女性指導員がビーチボールを参加者に渡しながら問う。「冷たいの反対なーに?」おばあちゃんが「あったかい!」と答える。そのビーチボールが自分に回ってきて「明るいの反対なーに?」・・・・「胸の中に鉄の玉ができて、焼けるほど熱くなる。まっ赤になって胸のなかでゴロゴロ転がる。われながらたまげる。激怒しているのだ。」そしてじぶんの怒りにたじろぎながら、心身の老いやそれへの焦り、諦観できないじぶんのいらだち、自分を区別し、他人にも区別してもらいたがったのだ、と書いている。
私もまたもう老いている自分を感じている。この文章を読みながら、私は過去長く、子どもたちを相手に、「大きいのどーれ?」「赤いのは?」などなど、無数の問いかけをしてきたことに、はっと気づいてしまう。子どもたちの成長・発達を願い、やったことは確かである。しかし、子どもたちの胸に「まっ赤な怒りがゴロゴロと転がる」現象が起きたかもしれない、そこまで感じとれていただろうか。子どもは言葉のあるなしに関わらず、皮膚や感覚で感じている。その心のうちを受け止め感じることもまた、子どもと対応する私たちの大事な力量とも言える。
前段で、辺見庸は施設の職員のやさしさにも触れている。「人間が人間に対してここまでやさしくしていられるわけがない・・・・といった猜疑心が去らない。」と。ここの職員は対応において、基本的にやさしくしできていると思っている。そしてそれは意識しないところまで来ていることも感じている。私がこの園の職員の子どもや家族への対応を見るに、「人間が人間に対してここまでやさしくしていられるわけがない」ほどのやさしさが自然にできているのを感じている。
しかし、辺見庸の文章は、その対応の内容に迫っていると言ってよい。子どもがそこにいたとき、発達や成長の遅い早いがあったとしても、内容において一人の人格として対応しているか、ということが問われているのに違いない。そして子どもたちの反応のなかにそのことを受け止め、感じているのかということである。若い職員たちはそうしたことを学んできたとは思うのだが、忘れずに永く心に留めておいてもらいたいと私は強く願っている。